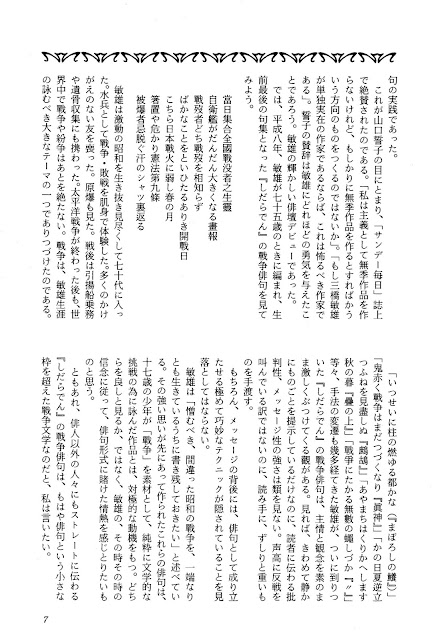『現代俳句』平成23年12月号 「直線曲線」より
大畑 等
現代俳句協会のホームページをご覧になったことはありますか?インターネットを使用されない方は、どなたかにお願いして是非ご覧下さい。現代俳句協会の歴史・組織のことをはじめ、行事や句会のことなど多方面にわたって掲載しています。
そのなかにインターネット(IT)句会があります。現代俳句協会会員に限らず、どなたでも参加出来るオープンな句会です。G1・G2のグレード制で、合計で毎月1800句ほど投句されます。会員の自己紹介欄を読みますと、様々な理由でインターネット句会に参加されていることを知ります。
※
「難病と共生しています」
「脳梗塞をして、左手リハビリの為PC(パソコン)を勉強中」
「車椅子の生活です。見たままの俳句と冬は頭の中で考えた俳句を作っています」
「白血病を俳句で乗り越えようとしています」
「若くして脳出血を患いましたが、リハビリ日記のような俳句を我流で始めてみました」
「音声で入力をしております」
このなかのお一人が、
徒競走歯をくひしばる青みかん 万里子
の句を投句されました。G1の901句のなかの一点句で高得点一覧から漏れてしまう句でした。講評では、「その他の注目句」欄を設け、たとえ無得点であっても私が感銘した句は取り上げるようにしています。この句の講評では「走者の緊張感は作者の緊張感でもあり、また『青みかん』のそれでもある。徒競走の情景が、座五の『青みかん』に収束され焦点を生みました。」と書きました。
実はこの原稿を書くにあたって、先ほど掲げた「自己紹介」のなかの一人と知り、感慨を深くしています。ああ、「歯をくひしば」っているのは、作者なのだと。
もう十数年も前のことと思います。新聞でほぼ一面を使って、インターネットの活用を訴えていたのは作家の水上勉でした。病気の人、高齢の人こそインターネットを活用して欲しい、ということでした。
水上勉は平成元年に心筋梗塞で倒れ、ペンを持つことが出来なくなりました。そこでパソコンを始めた、指一本でポツリ、ポツリとキーボードを打ったようです。そしてインターネットを始めました。夜中に目が覚めても、仲間にメールを送ることが出来る。電話の場合、ベルが相手を起こしてしまいますが、メールなら相手が起きたときメールを見ることになります。仲間との深夜のコミュニケーションにより、孤独感に陥ることはない。そのような訴えでした。
「インターネットの功罪」とか「インターネットは俳句をどう変えるか」という議論もありますが、身体的なハンディを負っている人の活用についても忘れてはいけないことと思います。俳句に限らず、「書きたい、綴りたい」という欲求に応えてくれるからです。
IT句会は投句者の相互選。G1会員の人はG1の句、G2会員の人はG2の句の選をします。そして感想や鑑賞を掲示板に書き込み、お互い楽しんでいるようです。投句者は毎月900句ほど読み、選をします(皆さんタフです)。ときどき類句・類想句の問題で掲示板に訴えがありますが、良識的な運びとなっています。
一人の人間に緩急があるように、IT句会でもそのときどきの緩急のリズムがあるようです。3月11日の「東日本大震災」後、4月、5月投句の句会では緊張感を感じました。そのなかから、いくつか抜き出してみます。
哀しくてどこからはじめよう さくら 良子
地震去りて囀り太郎かも知れぬ 樋口紅葉
先生と海底出でよ子供の日 高橋みよ女
最後に、最近のIT句会からいくつか抜き出して終わりとします。
嫁さんの風向き次第鉄風鈴 なにわの銀次
尻を拭く皺くちやの尻迎へ盆 小愚
半夏生姉の辞書より煙草の香 横田未達
稲妻を食らうて国語舌を出す 赤松勝
トラックに大首絵あり夏木立 小林奇遊
そら豆やこの世で礼の言えぬひと 吉村紀代子
らっきょ食む孔子の弟子となる日まで 陽南
ATMに指なめられしカフカの忌 おくだみのる
柿の木をどうする父の七回忌 本田信美
半夏生叩きたくなる尻がある 玉水敬藏
夏立つやぬうつと立てばぬうつとな 三休
荒縄の巻かるる地蔵花は葉に 坂東三郎
阿蘭陀の木靴売る店若葉風 高橋城山
笹粽雨の匂ひのしてゐたり 大塚正路
恋愛映画見て尾骨より新樹 木野俊子
紋黄蝶無言の吹き出しが舞う 中條啓子
2011年12月4日日曜日
2011年3月27日日曜日
北がなければ日本は三角
大畑 等
3月11日に発する「東日本大震災」。以来、夜、寝ている間もラジオをつけっぱなしでいる。眠っているのか起きているのか分からない日々。
東北地方の被害の大きさに震撼し、パソコンで津波に襲われた町の地図を見る。航空写真が地形を顕わにし、自分のなかで津波の恐怖を否応なく増大させる。そして津波に直面した人たちを思う。
寝不足でぼーっとした頭に、一冊の本の書名が思い浮かんだ。谷川雁の『北がなければ日本は三角』。「西日本新聞」に掲載された谷川最後の書き物であろう。幼い日々の回想を綴る、随想五十篇のなかの「北がなければ」から書名をとっている。
谷川家に「鼻歌から生まれてきたとでもいいたくなる、陽気なえくぼの小娘が登場」する。
―蚊帳の中の食事は、すこぶる彼女の気に入らないようでした。鍋にくっついている煮魚のしっぽを、平気で指でつまみあげ皿にのせたりします。そんな彼女の仕草を、だれか兄弟の一人が「きたない」と非難したときのことです。
彼女はいたずらっぽい目をくるっとさせ、あかるい音声で「北がなければ日本は三角」と応じました。この答は私たちを驚倒させました。父母ともに執着している清潔思想のお家芸が、軽いフックの一撃で吹っ飛とばされたからです。
私と弟は、寝室の蚊帳の釣り手をかわるがわる一箇ずつはずしては、三角になった日本を笑いながら検証しました。
満州事変(1931年)、五・一五事件(1932年)の頃であろう。十歳に達しようとする当時の谷川に向けて最晩年の谷川は推理する。大陸を含めた日本のかたちは四辺形だったが、幼い谷川はそれを円形として捉えていたようだ。それに対して海辺の娘の言葉は一撃を加えた。
―「あなたに北はあるの、それはどこ」という問いでもあると見れないこともありません。
この随想を書く谷川は地図を広げ、北海道東辺、小笠原諸島、与那国島を結ぶ。みごとな三角形、いつわりの所有(大陸)をとりのぞいた日本のすがた。
―彼女のいう、<北>とは<いつわりの領土>の意味だったのかと、つい深読みにおちいるほどです。
ともあれ、父が規定した検察官的な幼児期は、彼女のシンバルの一撃によってようやくゆらぎはじめ、私のなかの十代の独楽はあてもなく動きだすことになりました。
実は、私の頭に想起されたのは<三角>ではなくて「北がなければ日本は四角」であった。誤って想起されていた。本棚から取り出して私の思い違いが分かったのであるが、それには理由がある。四角は不安定なかたち、垂直性に欠ける、北があってこそ私たちは立つことができるのだ、三角形を成すことができるのだ、との思いが意識の下にあったからであろう。
熊野に生まれ育った私には<南>の「普陀洛」は肌に刷り込まれている。一方、北は希求するもの。谷川が言う「自分の精神をある透明な冷たさの極に集約する、<抽象としての北>」でもある。そんなことをいま思うのは戯言のように響くほど東北の被害は大きい。
私の東北の旅を、東北の友人を、津波におそわれた人たちを思う。一刻も早く北の町が復興して欲しい。
※『北がなければ日本は三角』著・谷川雁 河出書房新社刊
3月11日に発する「東日本大震災」。以来、夜、寝ている間もラジオをつけっぱなしでいる。眠っているのか起きているのか分からない日々。
東北地方の被害の大きさに震撼し、パソコンで津波に襲われた町の地図を見る。航空写真が地形を顕わにし、自分のなかで津波の恐怖を否応なく増大させる。そして津波に直面した人たちを思う。
寝不足でぼーっとした頭に、一冊の本の書名が思い浮かんだ。谷川雁の『北がなければ日本は三角』。「西日本新聞」に掲載された谷川最後の書き物であろう。幼い日々の回想を綴る、随想五十篇のなかの「北がなければ」から書名をとっている。
谷川家に「鼻歌から生まれてきたとでもいいたくなる、陽気なえくぼの小娘が登場」する。
―蚊帳の中の食事は、すこぶる彼女の気に入らないようでした。鍋にくっついている煮魚のしっぽを、平気で指でつまみあげ皿にのせたりします。そんな彼女の仕草を、だれか兄弟の一人が「きたない」と非難したときのことです。
彼女はいたずらっぽい目をくるっとさせ、あかるい音声で「北がなければ日本は三角」と応じました。この答は私たちを驚倒させました。父母ともに執着している清潔思想のお家芸が、軽いフックの一撃で吹っ飛とばされたからです。
私と弟は、寝室の蚊帳の釣り手をかわるがわる一箇ずつはずしては、三角になった日本を笑いながら検証しました。
満州事変(1931年)、五・一五事件(1932年)の頃であろう。十歳に達しようとする当時の谷川に向けて最晩年の谷川は推理する。大陸を含めた日本のかたちは四辺形だったが、幼い谷川はそれを円形として捉えていたようだ。それに対して海辺の娘の言葉は一撃を加えた。
―「あなたに北はあるの、それはどこ」という問いでもあると見れないこともありません。
この随想を書く谷川は地図を広げ、北海道東辺、小笠原諸島、与那国島を結ぶ。みごとな三角形、いつわりの所有(大陸)をとりのぞいた日本のすがた。
―彼女のいう、<北>とは<いつわりの領土>の意味だったのかと、つい深読みにおちいるほどです。
ともあれ、父が規定した検察官的な幼児期は、彼女のシンバルの一撃によってようやくゆらぎはじめ、私のなかの十代の独楽はあてもなく動きだすことになりました。
実は、私の頭に想起されたのは<三角>ではなくて「北がなければ日本は四角」であった。誤って想起されていた。本棚から取り出して私の思い違いが分かったのであるが、それには理由がある。四角は不安定なかたち、垂直性に欠ける、北があってこそ私たちは立つことができるのだ、三角形を成すことができるのだ、との思いが意識の下にあったからであろう。
熊野に生まれ育った私には<南>の「普陀洛」は肌に刷り込まれている。一方、北は希求するもの。谷川が言う「自分の精神をある透明な冷たさの極に集約する、<抽象としての北>」でもある。そんなことをいま思うのは戯言のように響くほど東北の被害は大きい。
私の東北の旅を、東北の友人を、津波におそわれた人たちを思う。一刻も早く北の町が復興して欲しい。
※『北がなければ日本は三角』著・谷川雁 河出書房新社刊
2011年1月2日日曜日
アンドレイ・タルコフスキーの芭蕉(下)
大畑 等
『ノシタルジア』はイタリアで撮影された。冒頭、出産の聖母(フランチェスカ)像が出てくるが、宗教的なモチーフはない、また哲学的でもない。ロシアには哲学は要らない、詩と文学がその代わりを果たしているから、と言われるが、もう一つ映画を加えてよいのかもしれない。
タルコフスキーは、ロシア人亡命者のロシアへの宿命的な愛着と、外国の生活を悲劇的なまでに受け入れられない同化能力の欠如を映画に撮りたかった。世界や自分とのあいだの深い不和、存在の全一性にたいするグローバルな憂愁、これらがノスタルジアを引き起こす、ノスタルジアという名の病だ、と彼は言う(撮影後、タルコフスキーもまたこの病をかかえることになる)。映画『ノシタルジア』では、主人公の生家、母、子供、妻、犬が出てくるが、これらはタルコフスキー自身のロシアそのものであろう。また水、瓶、雨はとりわけ美しい映像であるが、タルコフスキーはここに象徴もメタファーもないと言う。全身で感覚したそのものを映像にした、ということだろう。
 |
| 『映像のポエジア』より |
〈ノスタルジア〉という病をもったロシア人のゴルチャコーフは、イタリアにあって優柔不断、行動に首尾一貫性がない。異性からの愛にも応えられず罵倒される。対照的なのはパラノイア症者のイタリア人ドメニコである。彼はローマの広場で、人間性を踏みにじる今日の文明に抵抗しようと訴え、直後焼身自殺を遂げるが、所詮人々の目には茶番である(広場に持ち込んだカセットデッキから出るベートヴェンの交響曲第9番(歓喜の歌)がグニャリと間延びして途中で止まる。愛犬だけは状況を察知して吠える)。かつて彼は「世界の終わり」を悟って、家族を7年間監禁した。警察によって解放された子供は、山間の道路を走る車を見て「パパ、これが世界の終わり?」と訊ねる。ここでも彼の行動は茶番にされる。
しかし、主人公ゴルチャコーフはドメニコの「内的完全性」に感動し、彼との約束(ろうそくの火を消さずに温泉を渡る)を実行する。世間では意味のない行動をゴルチャコーフはやり遂げ、その後フィナーレである雪の廃墟のシーンに移る。さて芭蕉のこの句、
雪ちるや穂屋の薄の刈残し 芭蕉
世界からの孤絶と存在への懐疑をテーマにしたタルコフスキーは、廃墟(薄の刈残し=寺院)の中に廃墟(穂屋=生家)を見たのである。実際最後のシーンはトスカナの丘陵地帯とロシアの村が合体した映像である。
 |
| 『映像のポエジア』より |
また、『タルコフスキーの映画術』では以下のような記述がある。そのまま書き抜くと、
霧の中の秋雨!私の方にではなく隣家に向かって傘が音を立てて通りすぎる
[小夜時雨隣へ這入る傘の音]
嵐蘭の句であるが、句の前にある解釈はタルコフスキーのものか、ロシアの日本文学研究者のものかは不明である。いずれにしても「私の方にではなく」、「通りすぎる」が日本的抒情からすれば特異である。その解釈には個我意識の強い文化を感じる。対して私たちの文化は、かすかな「傘の音」に意識を向ける。しかし、異文化の文脈で読みとられる俳句に、私は大いに刺激を受ける。あまりにも現在の俳句が閉塞的だから。
(終わり)
2010年12月26日日曜日
アンドレイ・タルコフスキーの芭蕉(上)
大畑 等
雪ちるや穂屋の薄の刈残し 芭蕉
(岩波文庫『芭蕉七部集』)
ソ連を亡命同然に出たアンドレイ・タルコフスキー、彼の映画を最初に観たのは『ノスタルジア』であった。その後二三本観て、彼の著作を読んだ。そこでは石を組み上げていくような執拗な文体で、彼の映画の方法論が語られている。そのなかにすべり込むように俳句のことが書かれていた。しかし語り口は熱っぽい。抜き書きするとこうである。
-なんと簡潔で、また正確な観察だろうか!規則正しい知性、高尚な想像力!(略)
日本の詩人は、たった三行で現実に対する関係を表現できた。彼らは現実を観察しただけではない。観察しながら、その永遠の意味を、せかせかしたり、あくせくしたりせずに、呈示したのである。観察は正確で具体的であるほど、それはユニークなものになる、反復不可能なものであればあるほど、それだけイメージに近づく。(『映像のポエジア』より)
-それらは、自身以外には何も意味しない。と同時に、多くのものを意味するので、それらの本質を探究していくと、最終的な意味をとらえることが不可能になるのだ。言い換えれば、イメージがその使命に正直に一致すればするほど、それを何らかの理解可能な思弁的形式に押し込むことがますます困難になっていく。(『タルコフスキーの映画術』より)
雪ちるや穂屋の薄の刈残し 芭蕉
(岩波文庫『芭蕉七部集』)
 |
| 『映像のポエジア』より |
-なんと簡潔で、また正確な観察だろうか!規則正しい知性、高尚な想像力!(略)
日本の詩人は、たった三行で現実に対する関係を表現できた。彼らは現実を観察しただけではない。観察しながら、その永遠の意味を、せかせかしたり、あくせくしたりせずに、呈示したのである。観察は正確で具体的であるほど、それはユニークなものになる、反復不可能なものであればあるほど、それだけイメージに近づく。(『映像のポエジア』より)
-それらは、自身以外には何も意味しない。と同時に、多くのものを意味するので、それらの本質を探究していくと、最終的な意味をとらえることが不可能になるのだ。言い換えれば、イメージがその使命に正直に一致すればするほど、それを何らかの理解可能な思弁的形式に押し込むことがますます困難になっていく。(『タルコフスキーの映画術』より)
※『映像のポエジア』:(株)キネマ旬報社刊、『タルコフスキーの映画術』:水声社刊
ソ連に俳句が紹介された事情によると思われるのだが、タルコフスキーは俳句を発句と呼び、取りあげた句は芭蕉、嵐蘭など近世江戸俳諧のものである。冒頭の「雪ちるや」の句は翻訳者によって「雪散るや穂屋のすすきの刈り残し」と表記されているが、以下岩波文庫『芭蕉七部集』の表記に倣う。
この句に関する個人的な事情を書くと、この句はタルコフスキーの著書で初めて知ったと思っていたのだが、実は違った。芭蕉の句について書くにしろ読むにしろ何かと重宝している『芭蕉百五十句』(安東次男著・文春文庫)にはとりあげられていない。そこで本棚から茶色く焼けた、煙草のヤニの臭いのしみた岩波文庫『芭蕉七部集』を取り出し、この句が載っている頁を開けた(「猿蓑集 巻之一」におさめられている)。いつの頃か全く記憶にないが「残し」に赤ボールペンで傍線を引き「?」を付けているのを知った。頁下段の中村俊定の注を読むと、
穂屋の薄(ホヤノススキ 大畑ルビ)-陰暦七月二十七日、信濃諏訪神社の御射山祭に薄の穂で御仮屋を作る行事がある。これを穂屋の神事という。
とある。そうだ、日航機墜落事故のとき、私は御射山を訪れていたのだ。この句を当地で知り、その後俳句を始めてこの句を探したのかも知れない。さて、本題に。もう一度句を掲げると
(信濃路を過るに)
雪ちるや穂屋の薄の刈残し 芭蕉
タルコフスキーの著書でこの句を見たとき、あっ、これは彼の映画『ノスタルジア』のラストシーンそのものではないか!と思ったのである。タルコフスキーはこの句を掲げるのみで素通りしているが、もう語る必要がないほど彼の『ノスタルジア』を句は語っているのだろう、と私は想像した。
芭蕉のこの句の意は、「一面の枯れた薄原にいる。むこうに刈り取られた跡が見える。ぽっかりと穴が空いているようだ。刈り取られた薄は神事のための穂屋に使われた。しかしその穂屋も今は取り壊されてもう無いのだ。ああ、雪がちらついてきた」とこんなところだろう。伝統的な「わび・さび」を継承しながら、「刈残し」でもって俳諧の境地を打ち出していると思う。
一方、タルコフスキーは芭蕉の句をどうとらえたか?『ノスタルジア』の温泉のシーンで、半狂人ドメニコは語る。
「神は聖カテリーナに言った。『お前が存在するのではない。私が代わりに存在する』」
ソ連に俳句が紹介された事情によると思われるのだが、タルコフスキーは俳句を発句と呼び、取りあげた句は芭蕉、嵐蘭など近世江戸俳諧のものである。冒頭の「雪ちるや」の句は翻訳者によって「雪散るや穂屋のすすきの刈り残し」と表記されているが、以下岩波文庫『芭蕉七部集』の表記に倣う。
この句に関する個人的な事情を書くと、この句はタルコフスキーの著書で初めて知ったと思っていたのだが、実は違った。芭蕉の句について書くにしろ読むにしろ何かと重宝している『芭蕉百五十句』(安東次男著・文春文庫)にはとりあげられていない。そこで本棚から茶色く焼けた、煙草のヤニの臭いのしみた岩波文庫『芭蕉七部集』を取り出し、この句が載っている頁を開けた(「猿蓑集 巻之一」におさめられている)。いつの頃か全く記憶にないが「残し」に赤ボールペンで傍線を引き「?」を付けているのを知った。頁下段の中村俊定の注を読むと、
穂屋の薄(ホヤノススキ 大畑ルビ)-陰暦七月二十七日、信濃諏訪神社の御射山祭に薄の穂で御仮屋を作る行事がある。これを穂屋の神事という。
とある。そうだ、日航機墜落事故のとき、私は御射山を訪れていたのだ。この句を当地で知り、その後俳句を始めてこの句を探したのかも知れない。さて、本題に。もう一度句を掲げると
(信濃路を過るに)
雪ちるや穂屋の薄の刈残し 芭蕉
タルコフスキーの著書でこの句を見たとき、あっ、これは彼の映画『ノスタルジア』のラストシーンそのものではないか!と思ったのである。タルコフスキーはこの句を掲げるのみで素通りしているが、もう語る必要がないほど彼の『ノスタルジア』を句は語っているのだろう、と私は想像した。
芭蕉のこの句の意は、「一面の枯れた薄原にいる。むこうに刈り取られた跡が見える。ぽっかりと穴が空いているようだ。刈り取られた薄は神事のための穂屋に使われた。しかしその穂屋も今は取り壊されてもう無いのだ。ああ、雪がちらついてきた」とこんなところだろう。伝統的な「わび・さび」を継承しながら、「刈残し」でもって俳諧の境地を打ち出していると思う。
一方、タルコフスキーは芭蕉の句をどうとらえたか?『ノスタルジア』の温泉のシーンで、半狂人ドメニコは語る。
「神は聖カテリーナに言った。『お前が存在するのではない。私が代わりに存在する』」
続く
2010年12月19日日曜日
小野竹喬の「奥の細道句抄絵」
大畑 等
「現代俳句」平成22年11月号に菱沼多美子さんが「小野竹喬展を観て」と題するエッセイを書いています。今年の春に東京国立近代美術館で「生誕百二十年小野竹喬展」が開催されましたが、私も出かけました。展示の最後は「奥の細道句抄絵」十点でしたが、そのなかの一点はリーフレットに出ている、
田一枚植ゑて立ち去る柳かな 芭蕉
を絵にしたものでした。
「現代俳句」平成22年11月号に菱沼多美子さんが「小野竹喬展を観て」と題するエッセイを書いています。今年の春に東京国立近代美術館で「生誕百二十年小野竹喬展」が開催されましたが、私も出かけました。展示の最後は「奥の細道句抄絵」十点でしたが、そのなかの一点はリーフレットに出ている、
田一枚植ゑて立ち去る柳かな 芭蕉
を絵にしたものでした。
 |
| 「生誕百二十年小野竹喬展」リーフレットより |
西行に「道のべに清水流るゝ柳かげしばしとてこそ立ちどまりつれ」の歌がありますが、歌枕を訪ねる旅の芭蕉はこの柳のある蘆野の里(栃木県那須町芦野)を訪ねました。西行の歌の柳を芦野の柳に結びつけて伝承させたのは、謡曲「遊行柳(ゆぎょうやなぎ)」で、朽木の精が旅僧に報謝の舞をのこして消えるくだり。
荻原恭男は岩波文庫『芭蕉おくのほそ道』で、西行の和歌を「田一枚植て」に具象したところが俳諧である、と注をつけています。また、芭蕉の句の「立ち去る」は朽木の精が「消える」ことをふまえ、芭蕉は西行を偲びそして対話をしている、この句は概ねこういうことを背景にして鑑賞されています。つまり素直な嘱目の句とはとられてはいません。
しかし小野竹喬のこの絵には芭蕉の心理は描かれていません。芭蕉の句のなにを絵にしたのでしょうか?井本農一の『芭蕉入門』(講談社学術文庫)では以下のように書かれています。
-この句は、農夫や早乙女(さおとめ)たちが田植えをしているのを見るともなく眺めながら、遊行柳の下で西行との対話に耽っていた芭蕉が、田を一枚植えおわった人々の立ち去るのに、はっと我に返ったときの気持ちを読んだもののように、私は思われます。(p129)
井本農一の鑑賞は「柳かな」の「かな」を「ただいま、ここ」に重きをなした句の鑑賞。小野竹喬も同じ、芭蕉の心理的なもの(想起体験)ではなく「はっと我に返ったとき」風景を感覚する、それを絵にしたと私は思います。かたちと色を単純化して構成した象徴的な絵と言えましょう。
小野竹喬(おの ちっきょう:1889~1979)
笠岡市生まれの近現代日本画を代表する日本画家。晩年は日本の伝統的な大和絵(やまとえ)を新たに解釈し象徴的な世界に到達した。「奥の細道句抄絵(おくのほそみちくしょうえ)」は昭和51年の作。
【蛇足】
会場には竹喬筆の芭蕉の句も展示されていましたが、その端正な書に感動しました。俳句は松瀬青々(1869~1937)を師としたそうですが、竹喬の句は展示されていませんでした。師の青々の句は、
正月にちよろくさいことお言やるな 青々
元日の庭に真白の椿かな 青々
水にては水の色なる白魚かな 青々
2010年12月17日金曜日
「現代俳句」:無季俳句特集
小学生に人気ある句は、
戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺 白泉
狼に蛍がひとつ付いていた 金子 兜太
と聞きます。アニメ映画がつくるイメージが、これらの句を子供のこころに取り込ませたのでしょう。上の渡辺白泉の俳句(発表は昭和14年「京大俳句」5月号)は無季。新興俳句の代表的なこの句が子供の口から出るとは誰が想像したでしょうか。
「現代俳句」(現代俳句協会刊)平成22年11月号は無季俳句特集でした。ちょっと紹介、目次を覗いてみましょう。
(1)直線曲線-三橋敏雄の戦争俳句 遠山 陽子
(2)無季俳句考 林 桂
(3)江戸の無季俳句 川名つぎお
(4)『現代俳句歳時記・無季編』を読む 20名による鑑賞
となっています。いくつか抜き出してみます。
(1)より
-当時、「新興俳句がこんどの戦争をとりあげ得なければ、それは神から見放されたときだ」という山口誓子の言や、「青年が無季派が戦争俳句を作らずして、誰がいったい作るのだ」という西東三鬼の発言に鼓舞扇動されて、敏雄少年は無季俳句の制作に奮い立った。
-そのころの敏雄は、自分はあと二三年で兵隊にとられて戦死するだろうと思っていた。
(2)より
昭和21年土屋文明の「日本紀行」の文章を引いて
-「私は日本文学殊に和歌俳諧の類の優れた特色が、その季節感にあるといふ論に別に正面から反対する程の理由を持つて居ない。しかし日本文学の特色がいつもその季節感にありといふならばそれは吾々日本人にとつて淋しいことではあるまいか。吾々の文学がいつも季節感から出られないとすればそれは少なくとも日本人の生活能力の低調に関連する悲しむべきことではあるまいか。(後略:大畑)」
(3)より
徒行ならば杖つき坂を落馬かな 松尾芭蕉
襟にふく風あたらしきこゝちかな 与謝蕪村
松陰に寝てくふ六十余州哉 小林一茶
(4)より
昭和衰へ馬の音する夕かな 三橋 敏雄
鉛筆の遺書ならば忘れ易からむ 林田紀音夫
白線の内にかたまりいつか死ぬ 石川日出子
後ろにも髪脱け落つる山河かな 永田 耕衣
淋しさを許せばからだに当たる鯛 攝津 幸彦
無礼なる妻よ毎日馬鹿げたものを食わしむ 橋本 夢道
号泣やたくさん息を吸ってから 池田 澄子
強風の肉体旗もて巻かれたる 小川双々子
こめかみを機関車くろく突きぬける 藤木 清子
黄泉路にて誕生石を拾ひけり 高屋 窓秋
焼捨てて日記の灰これだけか 種田山頭火
鬼甍より恐ろしき鳩時計 山崎 尚生
ローソクもってみんなはなれてゆきむほん 阿部 完市
木の股の猫のむこうの空気かな 橋 閒石
彎曲し火傷し爆心地のマラソン 金子 兜太
切株は じいんじいんと ひびくなり 富澤赤黄男
うまく抱けない女のような木が一本 加藤 佳彦
戦争が廊下の奥に立つてゐた 渡辺 白泉
狼に蛍がひとつ付いていた 金子 兜太
と聞きます。アニメ映画がつくるイメージが、これらの句を子供のこころに取り込ませたのでしょう。上の渡辺白泉の俳句(発表は昭和14年「京大俳句」5月号)は無季。新興俳句の代表的なこの句が子供の口から出るとは誰が想像したでしょうか。
「現代俳句」(現代俳句協会刊)平成22年11月号は無季俳句特集でした。ちょっと紹介、目次を覗いてみましょう。
(1)直線曲線-三橋敏雄の戦争俳句 遠山 陽子
(2)無季俳句考 林 桂
(3)江戸の無季俳句 川名つぎお
(4)『現代俳句歳時記・無季編』を読む 20名による鑑賞
となっています。いくつか抜き出してみます。
(1)より
-当時、「新興俳句がこんどの戦争をとりあげ得なければ、それは神から見放されたときだ」という山口誓子の言や、「青年が無季派が戦争俳句を作らずして、誰がいったい作るのだ」という西東三鬼の発言に鼓舞扇動されて、敏雄少年は無季俳句の制作に奮い立った。
-そのころの敏雄は、自分はあと二三年で兵隊にとられて戦死するだろうと思っていた。
(2)より
昭和21年土屋文明の「日本紀行」の文章を引いて
-「私は日本文学殊に和歌俳諧の類の優れた特色が、その季節感にあるといふ論に別に正面から反対する程の理由を持つて居ない。しかし日本文学の特色がいつもその季節感にありといふならばそれは吾々日本人にとつて淋しいことではあるまいか。吾々の文学がいつも季節感から出られないとすればそれは少なくとも日本人の生活能力の低調に関連する悲しむべきことではあるまいか。(後略:大畑)」
(3)より
徒行ならば杖つき坂を落馬かな 松尾芭蕉
襟にふく風あたらしきこゝちかな 与謝蕪村
松陰に寝てくふ六十余州哉 小林一茶
(4)より
昭和衰へ馬の音する夕かな 三橋 敏雄
鉛筆の遺書ならば忘れ易からむ 林田紀音夫
白線の内にかたまりいつか死ぬ 石川日出子
後ろにも髪脱け落つる山河かな 永田 耕衣
淋しさを許せばからだに当たる鯛 攝津 幸彦
無礼なる妻よ毎日馬鹿げたものを食わしむ 橋本 夢道
号泣やたくさん息を吸ってから 池田 澄子
強風の肉体旗もて巻かれたる 小川双々子
こめかみを機関車くろく突きぬける 藤木 清子
黄泉路にて誕生石を拾ひけり 高屋 窓秋
焼捨てて日記の灰これだけか 種田山頭火
鬼甍より恐ろしき鳩時計 山崎 尚生
ローソクもってみんなはなれてゆきむほん 阿部 完市
木の股の猫のむこうの空気かな 橋 閒石
彎曲し火傷し爆心地のマラソン 金子 兜太
切株は じいんじいんと ひびくなり 富澤赤黄男
うまく抱けない女のような木が一本 加藤 佳彦
2010年12月11日土曜日
現代俳句協会と現代俳句
「現代俳句は難しいから」とのっけから言われることがあります。あたかも「現代俳句」というジャンルがあるかのように。これを金子名誉会長は『現代俳句年鑑』1989年版(現代俳句協会刊)できっぱり否定しています。「いま、現代俳句協会とは何か」というタイトルで金子兜太会長(当時)と松澤浩幹事長(当時)が対談、司会は前田吐実男年鑑部長(当時)です。これについての発言を抜き出して構成しましたが、今日にも真っ直ぐ通じる見解と言えましょう。
 |
| 左:金子会長(当時)と松澤幹事長(当時) |
以下、金子兜太会長(当時)の発言より
現代俳句協会を、現代俳句の協会だと考えている人が多いんです。そうしますと、現代俳句とはなんぞや、ということになって来るんだなあ。現代俳句協会というのは「現代」の俳句協会なんです。
戦後まもなくできたわけですが、あの時、第二次世界大戦後の時期を、現代と考えている、時代として現代と言おうとした傾向が強かったんです。それまで、明治以後は、近代という傾向だったんです。そのうちにちゃちゃらもちゃらになって、いつから近代だ、現代だとなって来たけれど、戦後当時は、時代区分が鮮明だったんです。
当初創設した石田波郷さんや西東三鬼さんたちが、戦後一番新しい組織内容をもった、われわれの理想とする俳句協会を作ろうじゃないか、そして作った。だから現代の俳句協会と言ったんです。したがって、現代俳句の協会ではありません。
私の中では、現代俳句という概念ははっきりしています。それは、現在ただ今を中心とした俳句だと思います。そして古き良きものを従属的な型、活用体として置くということです。古き良きものが主と考えるのが伝統俳句と考えます。伝統俳句なんて言うのは僭称であつかましい言い方だと思うけれどそれが、古き俳句なんです。現代俳句協会はそうではなく、あくまでも組織上の言葉です。(文芸理論上の、現代俳句とは何かと言い出すような)そんな狭いものを作ったわけではないのですから。(構成:大畑 等)
登録:
投稿 (Atom)